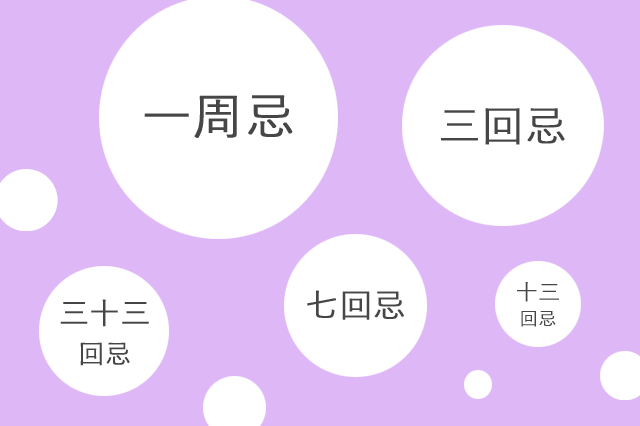お葬式終了後に行う主な法要は、四十九日法要と年忌法要(一周忌・三回忌…)です。年忌法要は毎年ではなく、「1 ⇒ 3 ⇒ 7 ⇒ 13…」と間隔が空きます。◯回忌は、基本的に3と7が付きます。
各法要年の祥月命日に法要を行うことが理想的ですが、実際にはご親族が集まりやすい祥月命日「前」の土日祝日に行います。
基本的な内容は、四十九日法要と同じですが、年数が経つにつれ小規模化し、七回忌以降はご家族のみで行うことが一般的です。
三十三回忌を最後の年忌法要とすることが一般的ですが、どこまで行うか?はご家族様の自由です。
また、宗派や地域によっても、法要のやり方は多少異なります。詳しくは菩提寺へご確認ください。

特別に年忌法要を気にせず、ご都合の合う日に親族が集まり、お墓参りに行く方もいます。
年忌法要を行う年の数え方
年忌法要を行う年の数え方は、少し注意が必要です。
まず、一周忌法要は、お葬式(死亡年)の翌年です。三回忌以降は死亡年を含めて数えますので、三回忌法要の場合は2年後に行います。
- 一周忌法要:お葬式の【翌年】に行う法要
- ◯回忌法要:お葬式から【◯-1】年後に行う法要
【2022年にお亡くなりになった場合】
- 一周忌法要:2023年(翌年)
- 三回忌法要:2024年(2年後)
- 七回忌法要:2028年(6年後)
【その他の法要】
- 13回忌:12年後
- 17回忌:16年後
- 23回忌:22年後
- 27回忌:26年後
- 33回忌:32年後(弔い上げ)
- 50回忌:49年後(弔い上げ)

「周忌」と「回忌」が違いです。ちなみに、回忌で言えば、お葬式が一回忌です。
なぜ、「3と7」の付く年に法要を行うの?
年忌法要を、「3と7」の付く年に行う理由には諸説あります。簡単に言えば、毎年法要を行うのは大変ですので、仏教で大切とされる数字「3と7」が付く年に法要を行う慣習ができたそうです。
「7」はお釈迦様が生まれた時に7歩歩いて「天上天下唯我独尊」と言ったこと。
また、六道(迷いある者が輪廻する世界)を超えて悟りに至る、つまり「六(6)を超える=7」という意味。
「3」は「2を超える」という意味です。
「有・無」「勝・負」「損・得」のように両極端に偏った考え方を離れ、中道(ちゅうどう)の生き方を意味します。
中道は、仏教では大切な考え方であり、お釈迦様も息子に「二を超える生き方をせよ」とおっしゃられています。
年忌法要を行うか?行わないか?
三回忌までは大切な法要とされていますので、三周忌まではきちんと行う方が多いように思います。七回忌以降は、僧侶を呼ばずに、ご家族・親族のみで「お墓参り+会食」で済ませる方も多いです。
基本的にはご家族様の自由ですが、菩提寺がある場合は、少なくとも一周忌法要までは行う流れになると思います。それ以降の具体的な日程や内容は、菩提寺とご相談ください。
無宗教の方(無宗教でお葬式を済まされた方)の場合
無宗教でお葬式を済まされた方や当社の僧侶紹介をご利用された方は、お葬式後の法要を行わない方も多いです。
もちろん、仏式の年忌法要に合わせて、ご親族が集まり故人様を偲んでお食事をされるのも良いと思います。

形式的な法要だけでなく、お墓参りやお仏壇にお供えをすることも立派な法要です。
年忌法要は祥月命日「前」の土日祝日に行います
他の法要と同じ様に、本来は「故人様の祥月命日(命日と同じ月日)」に行うことが理想ですが、多くが平日に当たりますので、実際には祥月命日「前」の土日祝日に行います。
まずは予定日を決めて、ご家族・親族に連絡をしましょう。参加人数を把握した上で、法要場所を決定することがおすすめです。年忌法要は徐々に小規模化していきますので、ご自宅で行う方が多いです。
ご親族の予定や仕事もありますので、最低でも2か月位前から少しずつ準備をしましょう。菩提寺にも早く予定を伝えれば問題なく対応していただけます。
法要は「何回忌」まで行うの?
「皆さん、何回忌法要までするんですか?」とよくご質問を受けます。
一般的には三回忌まで行う方が多いと思います。七回忌以降は形式的な法要は行わず、各家庭ごとのお墓参りやお仏壇へのお供え物をするなど、自由にされている方が多いです。
最後の年忌法要は「三十三回忌」
一般的には、三十三回忌(または五十回忌)を「弔い上げ」として、最後の年忌法要とします。
三十三回忌で故人様の霊がご先祖様の仲間入りをするとされています。また、法要を行う親族が世代交代をしているという理由もあります。
例えば、「祖父の三回忌」と「祖母の一周忌」が重なるというケースがあります。
「同じ年に法要が重る場合」や「翌年も法要が続く場合」は、まとめて一緒に行う場合もあります。これを「併修(へいしゅう)や合斎(がっさい/ごうさい)」といいます。
併修の場合、法要日は「命日の早い方」や「回忌数の少ない方」に合わせることが一般的です。
しかし、これは一般的な併修の考えですので、菩提寺(お付き合いのある寺)がある方は、事前に住職へご相談ください。
また、併修だからといって読経を2倍するわけではありませんので、御布施の金額も単純に2倍ではありません。その点も踏まえて、菩提寺とご相談ください。
年忌法要を行う場所・流れ・準備するモノ
年忌法要を行う場所は、ご家族・親族が集まりやすい場所を選びましょう。
- ご自宅
- 寺院・仏事料理店・ホテル
- 霊園内の法要施設
ご家族様のみなど、少人数の場合はご自宅が良いと思います。料理店やホテルをご利用の場合は、送迎バスのサービスも確認しましょう。
会場のご予約はお早めに
仏事料理店やホテル、霊園施設などを利用する場合は、早めの予約がおすすめです。
特に、お盆(8月)やお彼岸(3月・9月)の時期と重なると予約が取りにくいです。またお坊さん(僧侶)も法事が多くなりますので、早め早めの予約が必要です。
基本的に必要なもの
法要の内容にもよりますが、基本的に必要なモノは以下になります。
- 遺影写真
- ※遺骨(納骨する場合)
- ※埋葬許可証(納骨する場合)
- 本位牌
- お供え物・お花
- 御布施(僧侶への御礼)
忘れ物が無いように前日に再度確認しましょう。必要なモノは宗派により多少異なります。菩提寺(お付き合いのある寺院)へお問い合わせください。
年忌法要の内容と流れ
年忌法要の内容と流れは、四十九日法要や一周忌法要と基本的に同じです。
当日は現地集合し、僧侶を迎えて法要(読経・お焼香・法話)開式です。法要終了後にお墓参りと会食で法要終了です。
必ず僧侶より先に到着しましょう。
喪主様が代表してあいさつ。
読経・お焼香・法話。約1時間ほど。
お墓参りに霊園へ移動。(※納骨予定の方は、僧侶同席で納骨式)
会食をして法要終了。会食をしない場合もあります。

僧侶が会食に同席されるか?は、事前に確認しましょう。
服装について
特に決まりはありませんが、略礼装(色は黒)が基本です。主に男性はスーツ、女性はワンピース・アンサンブルを着用、学生は制服で構いません。
ご家族だけの場合は、落ち着いた色の平服(普段着)で行う方もいらっしゃいます。
御布施について
御布施(僧侶へのお礼)の金額は、平均3~5万円程です。封筒の表書きは「御布施」とします。
遠方から僧侶に来ていただく場合は「お車代」。また、一緒に会食されない場合は「お膳料」として、各5,000円~10,000円程度をお包みします。あくまで一般的な金額ですので、迷った場合は菩提寺へお尋ねください。
まとめ
お葬式後の法要は、四十九日法要・一周忌・三回忌法要までが最も大切とされています。
しかし、「ご家族・親族だけで行うお葬式=家族葬」が増加しているように、法要も同様に小規模化・省略傾向にあります。
法要を行うか?行わないか?は基本的にご家族様の自由です。無理に行う必要もないと思います。あまり形式的な考えにとらわれず、各ご家庭に合ったスタイルで供養することも大切です。

命日にお写真に手を合わせたり、お好きだった食べ物をお供えするだけでも良いと思います。
関連ページ
 一周忌法要
一周忌法要
お問い合わせ
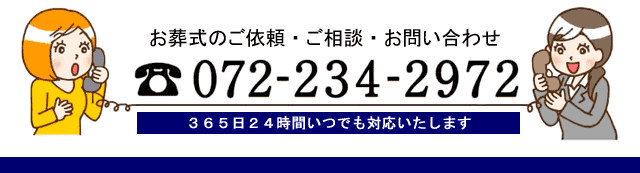
新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL. 072-234-2972