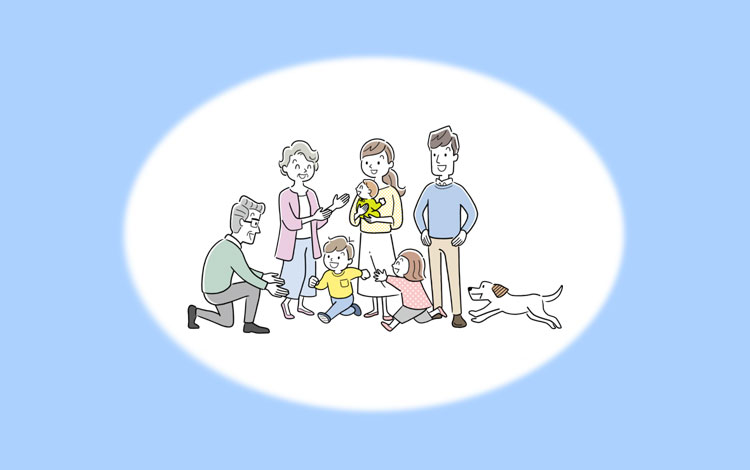「相続税の金額ってどのくらい?」と気にされる方もいらっしゃると思いますが、ここ数年のデータでは相続税が課税された人は毎年約10%です。約90%の人は相続税の対象外(相続税は0円)ですので、相続税はあまり不安にならなくても良いと思います。
相続税を課税された人の割合
2021年:9.3%、2022年:9.6%、2023年:9.9%
<令和5年(2023) 国税庁データより>
今回お伝えしたい事は、多くの人にとって【相続「税」対策は不要でも、相続対策は必要です】という事です。
ここで言う相続対策は、もしもの時のための「ご家族・親族全員での話し合い」です。後で後悔しないために、お葬式や相続(財産の分配)についてお互いの希望や気持ちを伝える事はとても大切だと思います。
子から親御さんへ「お葬式や相続」の話を切り出すのは勇気がいるかもしれませんが、後で後悔するよりも思い切って話をしてみることがおすすめです。
お葬式や納骨等については、価値観は様々ですので自由で良いと思います。財産(相続税)については、私個人としては信頼している司法書士・税理士さんとの会話からの結論は以下の通りです。
- もし自分が【財産を引き継ぐ側(相続人)】の場合、相続税の支払いが必要な場合は支払う。
- もし自分が【財産を残す側(被相続人)】の場合、特別に相続税対策はしない。財産はシンプルが最適。
再度お伝えしますが、約90%の人は相続税の対象外です。相続税対策よりも重要なのは、お葬式後もご家族・親族が仲良く過ごしていくことだと思います。
ここから先の内容は個人的な意見も含まれますし、相続税対策【自体】を否定するわけではありません。あくまで考え方の1つとしてご理解いただければ幸いです。
約90%の人は相続税の対象外(相続税は0円)です
冒頭でお伝えしたように、約90%の人が相続税の対象外(相続税は0円、支払い不要)です。
まず、相続税が課税されるか?されないか?の基準についてですが、相続税には「基礎控除」があり、故人の財産が基礎控除額を超えなければ相続税はかかりません。
【3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)】
例えば、夫が亡くなり、妻と子2人(合計3人)が相続人の場合
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円になります。
故人(被相続人)が残した財産が「基礎控除額を超えるか?超えないか?」を調べる必要がありますが、実際には「約90%の人が相続税の対象外=基礎控除額を超えない」と考えると、あまり不安にならなくても大丈夫だと思います。
また、財産に不動産(土地・建物)が含まれる場合は評価額の判断が難しいと思いますので、気になる場合は司法書士・税理士さん、不動産会社等へのご相談も良いかも知れません。葬儀社さんに専門家を紹介してもらうのもおすすめです。
相続税は故人が残した財産の「時価」に対して課税されます。
不動産(土地)の時価の計算方法の1つとして【路線価(ろせんか)方式】があります。
路線価方式は、国税庁が公表している「路線価(1㎡あたりの土地の価格)」に「土地の面積」を掛けて評価額を出す方法です。
その計算に必要な情報は以下の「3点」です。
1.路線価
国税庁のHPで「路線価図」を確認できます。
例えば、所有している不動産の前の道に「200 C」と表記がある場合、200は「200千円」のことで1㎡辺り200,000円です。後ろのA~Eのアルファベットは借地権割合ですが、借地権でない場合は関係ありません。
2.持分割合(誰かと共有で所有している場合)
土地を誰かと共有で所有している場合は、その人の「持分割合」を調べる必要があります。そのためには法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取り、持分割合を確認しましょう。
3.土地の面積(㎡)
毎年4~5月頃に市町村から届く「固定資産税の納税通知書」に「土地の面積(地積)㎡」で確認できます。
例えば、上記3つの情報を確認し、所有している不動産が「路線価20万円、持ち分1/1、面積200㎡」であれば
「20万円×1/1×200㎡=4,000万円」が評価額になります。
税務署から「相続税についてのお尋ね」の文書が届いた場合
故人(被相続人)が一定以上の財産を持っていた場合、税務署から相続人へ「相続税についてのお尋ね」という文書が
お葬式を終えてから数か月後に届くことがあります。
その理由は、まず人が亡くなった場合に必ず死亡届を役所に提出しますが、その情報は税務署にも報告されます。そして、税務署は故人の財産を調査して「相続税についてのお尋ね」を一部の人に送ります。
ただし、「文書が届いた=必ず相続税の申告が必要」というわけではありません。もし文書が届いた場合は、相続専門の税理士さんにご相談ください。
相続(相続税)のお悩みは「相続に詳しい」専門家に相談しましょう
相続関連の主な相談先(専門家)は「弁護士・司法書士・税理士」の3士業になりますが、選ぶ際の重要ポイントは「相続に詳しい(相続分野を取り扱っている)」です。上記の3士業であっても相続に対応していない場合があります。
次に、各士業で専門分野は異なります。
- 弁護士
相続人間での紛争解決(その他にも幅広く対応可能で万能) - 司法書士
不動産の名義変更(相続登記 ※令和6年から義務化) - 税理士
相続税の相談・申告
※相続放棄をご希望の場合は、弁護士または司法書士にご相談ください。
最初の相談先がどこであったとしても、他の士業と連携して問題解決していただけるはずですのでご安心ください。
もし知人に専門家(上記の3士業、その他に社労士・行政書士など)がいらっしゃる場合は、まずはその人に相談しましょう。
相続「税」対策(保険や不動産)は不要です
※あくまで個人的な意見としてご覧ください。
冒頭でお伝えしたとおり、私個人としては信頼している司法書士・税理士さんとの会話からの結論として、相続税対策は不要だと考えています。
- もし自分が【財産を引き継ぐ側(相続人)】の場合、相続税の支払いが必要な場合は支払う。
- もし自分が【財産を残す側(被相続人)】の場合、特別に相続税対策はしない。財産はシンプルが最適。
財産を1円でも多く残したい場合は対策の余地があるかもしれませんが、個人的には「相続税がかかる場合は支払う」が良い思います。
よく相続税対策として「保険や不動産」の2つが取り上げられますが、どちらも不要です。
特に不動産での「相続税対策の賃貸アパート建築」は要注意です。素人が手を出すべきではありませんので、ハウスメーカー・不動産会社からのこの種の営業は断ることがおすすめです。
そもそも約90%の人が相続税の対象外(故人の財産が基礎控除を超えない)です。そのため、相続税対策として新たに何かを契約・購入することは基本的に不要と考えて良いと思います。
結論として、財産を残す側・受け継ぐ側、どちらの立場だったとしても、財産はシンプルが最適だと思います。
▼【参考情報】:ご興味のある方はご覧ください。※クリックをすると開きます。
※あくまで個人的な意見としてご覧ください。
保険は本来「低確率だけど、起こってしまうと損失大」のリスクに備えるものです。例えば、小さなお子さんがいるご家庭の場合、もし一家の大黒柱が死亡した場合のリスクに備える「死亡保険(掛捨て型)」は必要です。
でも、相続「税」が安くなれば良いだけの保険は本来の役割ではないため不要だと思います。
もし相続対策に保険を活用する場合は
・保険を使わないと、相続税の納付に必要な現金が不足する
・保険を使わないと、相続人にバランスよく現金を配分できない
など「現金が不足するリスク」に備える場合は検討の余地はあるかもしれません。
インターネットで「相続税対策 保険」と検索すると、よく「貯蓄型保険(終身・養老など)」を見かけますが、相続に関係なく、そもそも貯蓄型保険自体がおすすめではありません。
貯蓄型保険の中身は「保険(薄い保障の掛け捨て型)+投資(手数料が非常に高い投資信託)のセット商品」です。
投資商品が含まれていますし、短期解約では元本割れもします。保険商品を保険会社から購入するのは当然ですが、投資商品は「証券会社からご自身で購入する」が基本です。わざわざ保険会社を通して購入すると手数料が非常に割高です。
大前提として、貯蓄型保険でお金は増えません(仮に少し増えた場合でも、利益の大部分を保険会社に取られています)。もし貯蓄が目的であれば、保険ではなく金融口座に貯めておきましょう。
「保険は保険、投資は投資、貯蓄は貯蓄」と分けて考えることがおすすめです。
いずれにしても、相続「税」対策の保険は基本的に不要だと思います。
※あくまで個人的な意見としてお考え下さい
例えば、現金で1億円を持っている場合より、賃貸住宅を1億円分持っている方が相続税は安くなります。その理由は、法律上、賃貸住宅は時価の6~7割くらいで評価され、資産額が減って相続税を圧縮できるからです。
そのため、相続税対策の「賃貸アパートの建築」が近年増えているようです。でも、賃貸アパート建築はプロでも失敗する可能性がある難しい事業です。ただでさえ、日本では人口減少で空き家が増えていますので、素人は避けた方が良いです。
確かに、不動産(土地)を用いた相続税対策が有効な場合もあります。ただし、それはプロの不動産投資家が行う場合に限って効果的であって、素人の場合は失敗するケースが非常に多いです。
仮に相続税が節税できたとしても、節税額以上に費用(金利・建設費・修繕費等)が掛かったり、膨大な時間と手間の割にお金が手元にほとんど残らず、最終的には家賃の下落や空室で困るリスクを背負う可能性もあります。
不動産は長期目線かつ緻密な計算で総合的に考える必要があり、素人が手を出すと非常に危険です。
もし親御さんが不動産(空き地)を所有されている場合は、悪質な営業に注意が必要です。不動産(空き地)の所有者は法務局で調べれば誰でも分かります。「お子さんに収益物件(賃貸アパート)を残しませんか?」などのハウスメーカー・不動産会社からの営業は断りましょう。
私の知人にも、親御さんが知らない間に不動産を増やしていて、処分に苦労した人がいます。不動産は大きな財産ですし、管理や処分も簡単ではありませんので、ご家族全員で話し合っておくことが大切です。
財産はシンプルが最適
故人(被相続人)が色々なモノを残すと、相続人であるご家族・親族が後々苦労する可能性もあります。もし私が財産を残す側であれば、極力シンプルにしたいと考えています。
- 金融・証券口座は各1つ
- クレジットカードは1枚
- その他の財産情報はエンディングノート等に一覧表でまとめる
財産がシンプルであれば、引き継ぐ側(相続人)も非常に助かると思います。
再度お伝えしますが、約90%の方が相続税はかかりません。相続「税」対策は基本的に不要です。そもそも相続税が対象外の人に「相続税対策になりますよ」と不要な保険等を営業してくる(既に営業を受けている)ケースもあるかもしれません。
もしご自身が財産を残す側(被相続人)の場合、相続人(ご家族・親族)のことを想う気持ちはとても理解できますが、お葬式後に複雑な手続きが発生する(または、そもそも不要な)相続「税」対策よりも、財産はシンプルが最適だと思います。
ざっくりとした計算でご説明(1~5)しますのでご容赦ください(生前贈与や保険金控除、借金などは除きます)。
1.例えば、夫(故人)が1億円の財産を残し、妻と子2人(合計3人)が相続人の場合
- 基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
- 課税金額(相続税の対象となる金額):1億円-4,800万円(基礎控除)=5,200万円
2.次に、この5,200万円を「まず法定相続分で分けると仮定」して計算します。
法定相続では「妻:50%、子:50%(2人の場合、各25%ずつ)」になりますので
- 妻(50%):2,600万円
- 子(50%を人数で割る):1,300万円(1人当たり)
3.相続税額は「1,000万円超~3,000万円以下の場合:税率15%、控除額:50万円」なので
- 妻:2,600万円×15%-50万円=340万円
- 子:1,300万円×15%-50万円=145万円(1人当たり)
4.すべて(3人分)を合算すると、相続税の総額は340万円+145万円+145万円=630万円
この630万円を「実際に相続した割合」に応じて納付税額を計算します。ここでは法定相続分と同じく「妻:50%、子:50%(2人なので各25%)」で相続したとします。
- 妻(50%):315万円
- 子(50%を人数で割る):157万5千円(1人当たり)
5.最終的に支払う相続税は
- 妻は「配偶者の税額軽減」により納付税額は【0円】
- 子の納付税額は【各157万5千円】
相続対策「ご家族・親族全員でお葬式や相続(財産の分配)についての話し合い」は必要です
繰り返しになりますが、相続税は約90%の人が対象外(相続税は0円)ですので、相続「税」対策は基本的に必要ないと思います。
でも、相続対策は必要です。それは「ご家族・親族全員での話し合い」です。
ご家族・親族で話し合う内容
- どんなお葬式が良いか?
- どこに納骨(遺骨の供養)するか?
- 財産をどの様に分けるか?
- その他に伝えておきたい希望やメッセージ
お葬式や納骨、相続(財産の分配)、その他気になる事について、お互いの希望や気持ちを素直に伝えておくことはとても大切だと思います。
実際、お葬式中に喪主やご遺族様とお話しすると、「あの時●●していれば…」と多くの人が後悔をお持ちです。でも、ご自身の行動次第で後悔をなくす事もできるかもしれません。
- 財産を残す、見送られる側(被相続人)
- 財産を引き継ぐ、見送る側(相続人)
どちらの立場であっても、ご家族・親族が仲良く過ごしていくことが重要だと思います。もしお時間に猶予がある場合は、一度話し合うことがおすすめです。きっと価値のある時間になると思います。
お互いの気持ちは話さないと分かりません
例えば、財産を残す側(親)と引き継ぐ側(子)では希望が正反対かもしれません。
親御さんは一般的に
家族(子や孫)に少しでも財産を残してあげたい
と考える方が多いです。
でも、お子さんは
財産は全部使って、残りの人生を豊かに楽しく過ごして欲しい
と思っているかもしれません。
お互いの気持ちは話し合ってみないと分かりません。人によっては話すことが難しい、少し恥ずかしい部分もあるかもしれませんが、後で後悔するよりも思い切って話してみてはいかがでしょうか?
まとめ
相続「税」対策については、その人の立場や状況によって様々な意見があると思いますので、相続税対策「自体」は否定しません。ただし、不要な相続税対策の保険や不動産(特に賃貸アパート建築)の悪質な営業にはご注意ください。
あくまで個人的な意見として、相続税対策は不要だと考えています。
- もし自分が【財産を引き継ぐ側(相続人)】の場合、相続税の支払いが必要な場合は支払う。
- もし自分が【財産を残す側(被相続人)】の場合、特別に相続税対策はしない。財産はシンプルが最適。
そもそも約90%の人が相続税の対象外(相続税は0円)ですので、あまり気にされなくても良いと思います。
もし相続(相続税)に関して気になる点がある場合は、相続に詳しい専門家(弁護士・司法書士・税理士など)にご相談ください。
多くの人にとって、相続税を気にするよりも重要な事は、お葬式後に残されたご家族・親族が仲良く過ごしていくことだと思います。そのための相続対策=お葬式や相続(財産の分配)についての話し合いは本当に大切です。
- もしもの時に困らない
- お互いの気持ちを知っておきたい
- 後で後悔をしたくない
人によっては話すことが難しい、恥ずかしい部分もあるかもしれませんが、思い切って気持ちを伝えてみることがおすすめです。
「自分から勇気を出して行動していれば回避できた事に対して、行動できずに後で後悔してしまう」
これは私自身も経験している事です。
ここまでお付き合いいただいた方には、後悔してほしくないと心から思っています。