ご遺骨をいくつかの骨壺に分けて収骨し、別々の場所へ納骨・供養することを「分骨(ぶんこつ)」といいます。
実際に、ご遺骨を2か所以上に納骨することはよくあります。例えば、「1つは菩提寺(お寺)、もう1つは先祖代々のお墓」が最も多いです。
基本的には、お葬式の打ち合わせ時にスタッフが【納骨先・骨壺のサイズ・将来の予定】などをお聞きして、分骨が必要かどうか?を判断し必要な手続きも済ませますので、ご安心ください。
分骨を行う主な3つの場面
- 収骨の時点で分骨
- 収骨後の骨壺から分骨
- 既にお墓などに納骨済みの骨壺から分骨
状況によって必要な手続きと申請先が異なります。
分骨証明書の発行
ご遺骨をいくつかに分けて、別々の場所に納骨するには「分骨証明書」が必要です。分けたご遺骨が ”間違いなく故人様の遺骨である” という証明書です。
通常、故人様お一人に対して【埋葬許可証】が火葬終了後に発行されます。「お骨壺1つ+納骨先が1か所」であれば、この埋葬許可証1枚の提出で大丈夫です。
追加でお骨壺を増やす場合に、追加数に応じて【分骨証明書】が必要です。分骨証明書がなければ、追加したお骨壺(遺骨)を納骨することができません。
分骨のタイミング
分骨を行うタイミングで最も多いのは、「収骨(お骨上げ)時点」です。
お葬式の打合せ時に「遺骨(お骨壺)を分けて納骨したい」とご相談いただければ、当社スタッフが分骨証明書発行手続きとお骨壺を準備いたします。

書類手続きやお骨壺の準備が必要ですので、火葬日の前日までにご連絡ください。
例えば、「遺骨を2つに分けて、1つはお墓・もう1つは手元供養で自宅で祀る予定」だとします。
基本的に手元供養用の遺骨は少量で納骨しないので、分骨証明書は必要ないといえば必要ありません。
しかし、将来どこかに納骨する可能性がある場合は、分骨証明書をお持ちの方が安心です。
まだ納骨前の骨壺から分骨する場合
1か所に納める予定でお骨壺1つで収骨した後、「やっぱり、別の場所にも納骨したい」という場合もあります。
まだ、納骨していない(ご自宅にある)お骨壺から分骨をする場合は、火葬を行った火葬場(斎場)または市町村へ分骨証明書の発行申請をしましょう。
お骨壺を準備して、ご遺骨を分ける作業はご家族で行っても問題ありません。
既にお墓などに納骨をした骨壺から分骨する場合
納骨後に「やっぱり、自分(次男)のお墓にも両親の遺骨を納めたい」などの理由で、分骨を希望される方もいらっしゃいます。
お墓の管理者に事情を説明して、分骨証明書の発行と分骨作業を依頼しましょう。新たに納骨する場所の管理者に分骨証明書を提出すれば、納骨が可能です。
寺院墓地の場合は分骨法要などを行うこともありますので、詳しくは菩提寺にご確認ください。

お墓の納骨室(カロート)の開閉作業に費用が必要な場合があります。
基本的には霊園スタッフがサポートしてくれますが、古いお墓の場合はご自身で石材店に依頼が必要な場合もあります。
埋葬許可証や分骨証明書を紛失した場合は再発行が必要
もし、埋葬許可証・分骨証明書を紛失した場合は再発行が可能です。火葬を行った火葬場または市町村、もしくはお葬式を依頼した葬儀社さんにお問い合わせください。
霊園や寺院から発行された書類を紛失した場合は、霊園や寺院にお問い合わせください。
 埋葬許可証の紛失した場合の再発行手続き
埋葬許可証の紛失した場合の再発行手続き
【参考】改葬(かいそう:お墓の引越し)について
近年、先祖代々のお墓を墓じまいして、よりご家族・親族にとって都合の良い場所に移す方が増えています。この様なお墓の引越しを「改葬」と言います。
「墓じまい」の方が世間一般的には認知さていますが、厳密には異なります。
- 墓じまい=墓石を撤去し更地に戻して、霊園管理者に返す
- 改葬=墓じまい+遺骨の移動

同じ意味で使われている感じですが、特に問題はありません。
改葬
改葬は、納骨(埋葬)されていた遺骨を、別のお墓や納骨堂へ移すことです。
「墓地、埋葬等に関する法律」 第1章第2条
「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
※墳墓:死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設
個別収骨タイプの納骨堂内での場所移動は改葬に当たりません。施設全体が1つのお墓と考えるからです。また、お墓をリフォーム中に一時的に自宅で遺骨を保管し、完成後にお墓に戻すのも改葬ではありません。
また、取り出した遺骨を「海洋散骨」する場合は改葬ではありません。改葬の定義は、「別の場所へ埋葬・収蔵すること」だからです。別のお墓や納骨堂などへ移動・納骨しない「海洋散骨」は改葬に該当しません。
改葬には役所での手続きが必要です
- 新しい墓地や納骨堂の決定と「受入許可書」の発行
- 改葬許可申請書(現在のお墓のある市町村で発行)に現在のお墓の管理者のサインと証明印
- 改葬許可書を市町村に提出し、改葬許可書を受け取る
- 現在のお墓から遺骨を取り出し、更地に戻す
- 新しいお墓・納骨堂に遺骨と改葬許可書を提出し、納骨
改葬を行うには「現在のお墓がある市町村」で申請し、改葬許可を受ける必要があります。また、現在のお墓の管理者・新しいお墓の管理者、両方の署名も必要です。

お墓の土(霊土)の移動は、分骨でも改葬でもありません。分骨・改葬の対象は、あくまで「遺骨」です。
ただし、多くの土を移動・埋蔵する場合は、新しい墓地の許可が必要な場合があります。
まとめ
分骨を希望する理由は様々ですし、遺骨をどのように供養するかはご家族の自由です。しかし、親族間でトラブルになるような事は避けましょう。
実際に「お墓参りに故郷に帰るとお墓が無くなっていた」という事もあります。ご親族(お墓の使用者)が連絡も無く独断で “墓じまい” をしてしまったようです。
お墓・遺骨はご家族・親族に関わる大切なものですので、全員に納得していただくことが重要です。
お問い合わせ
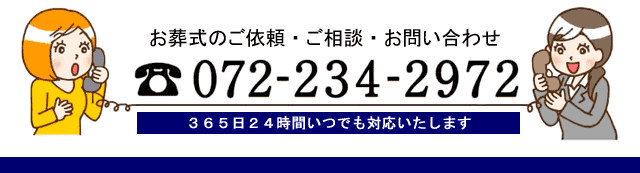
新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL. 072-234-2972
