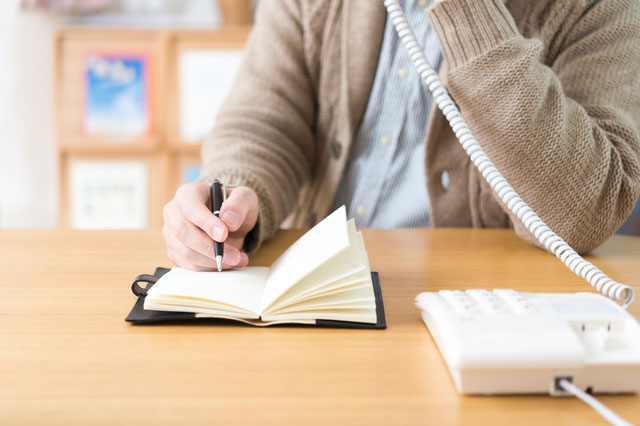ご遺骨をお墓や納骨堂へ埋葬するためには、【埋葬許可証(または分骨証明書)】が必要です。埋葬許可証は、火葬・収骨が終了した時点で、火葬場(斎場)スタッフから喪主様(またはご遺族)へ手渡されます。
もし、埋葬許可証や分骨証明書を紛失した場合は、再発行(再交付)が可能です。スムーズに手続きが進めば1日で完了します。まずは、「火葬を行った火葬場(または役所)」や「お葬式を依頼した葬儀社」へお問い合わせください。

火葬場がお近くの場合は当日再発行が可能ですが、納骨予定日が近い方はご注意ください。
「納骨の時に忘れないように!」と、骨箱(骨壺が入っている箱)の中に埋葬許可証が保管されている事が多いです。
封筒(火葬場発行の封筒)の中に折りたたまれた状態で入っていると思いますので、一度ご確認ください。
まず最初に、埋葬許可証の交付までの流れ
再発行手続きのご説明の前に、埋葬許可証が交付されるまでの流れを簡単にご説明します。
- 役所へ死亡届提出、役所から「火葬許可証」が交付
- 「火葬許可証」を火葬場へ提出
- 火葬・収骨終了後に火葬場から「埋葬許可証」が交付
1~2は葬儀社スタッフが代行します。3火葬・収骨終了後に、火葬場スタッフから喪主様(遺族)に「埋葬許可証」が手渡されます。
再発行の手続きは1~3の逆をたどります
再発行は基本的に上記の逆をたどりますので、最初は火葬場へのお問い合わせがおすすめです。ただし、火葬場の電話番号が掲載されていない市町村も多いので、その場合は役所へお問い合わせください。
「火葬許可証」と「埋葬許可証」が別々のようにご説明しましたが、最近では2つを一体にした「火(埋)葬許可証」という1枚の用紙(A4サイズ)になっている市町村が多いです。※「分骨証明書」は別途発行になります。
役所で火葬許可証が交付され、そこに火葬場職員が火葬日時・執行印することで、埋葬許可証としても使用可能になります。そのため、最初から表題が「火(埋)葬許可証」として役所で交付されます。
埋葬許可証の再発行は、まず火葬場(または役所)へお問い合わせください
埋葬許可証(または分骨証明書)を紛失した場合は、再発行(再交付)が可能です。まずは「火葬を行った火葬場(斎場)・市町村の役所」へお問い合わせください。
再発行までの基本的な流れ
まず、【火葬を行った火葬場(斎場)】で「火葬証明書」を発行してもらいます。
火葬証明書を【死亡届を提出した役所】へ提出し、「埋葬許可証」の再交付申請をします。
役所から再発行された「埋葬許可証」を受け取り、手続き完了です。
「役所で火葬許可証の発行 ⇒ 火葬場で埋葬許可証の発行」の逆をたどるイメージです。スムーズに進めば1日で完了します。市町村によって少し手続きが異なりますので、窓口でご確認ください。あくまで基本的な手順ですので、役所での手続きだけで再発行可能な市町村もあるようです。
また、霊園によっては火葬場(斎場)が発行する「火葬証明書」のみで納骨可能な場合もあるようです。各霊園の規則も一度ご確認ください。
※少し分かりにくい部分もあるので、直接電話でされるのがおすすめです。

火葬場の電話番号が掲載されていない市町村ホームページもありますので、最初は火葬場を管轄する役所への電話がおすすめです、
火葬場(斎場)の調べ方
火葬場の多くが公営で各市町村が運営しています。また、火葬場は「故人様の住所地の火葬場を利用する」が一般的です。例えば、故人が堺市民の場合は堺市の火葬場(堺市立斎場)を利用します。
インターネットで調べる場合は「◯◯市 火葬場」で大丈夫だと思います。はっきりと思い出せない場合は、お葬式を依頼した葬儀社に確認しましょう。
再発行に必要な物
基本的に必要な物は下記になります。また、郵送での申請も可能ですので、詳しくは窓口にお問い合わせください。
- 申請書
- 申請者の身分証明書(免許証など)
- 申請者の認印(朱肉を使うもの)
- 申請者と死亡者との続柄がわかる書類(戸籍謄本など)
- 発行費用:数百円程度

故人名(漢字)、住所、生年月日、死亡日、火葬執行日などを聞かれる場合もありますので、事前に準備をしておきましょう。
分骨証明書の再発行も同じ手続き
通常、故人様1人(骨壺1つ)に対して「埋葬許可証」が1枚発行されますが、それとは別に追加したお骨壺の数だけ「分骨証明書」が発行されます。
- お骨壺2つで収骨:埋葬許可書1枚+「分骨証明書1枚」
- お骨壺3つで収骨:埋葬許可書1枚+「分骨証明書2枚」
※お骨壺2つ以上で収骨した場合、埋葬許可証とは別に「分骨証明書」が発行されます。
分骨証明書を紛失した場合も、火葬場(斎場)または市町村の役所へ連絡をして再発行が可能です。
お墓や納骨堂の管理者から交付された分骨証明書の場合
お墓や納骨堂に納めた骨壺から「やっぱり他の場所にも納骨したい」などの理由で、遺骨の一部を取り出す(分骨する)方もいらっしゃいます。この場合、霊園管理者から「取り出した遺骨に対する分骨証明書」が発行されます。この書類を紛失した場合は、霊園管理者に再発行を依頼しましょう。

民間霊園から発行された書類の再発行は、各管理事務所へお問い合わせください。
まとめ
埋葬許可証や分骨証明書の再発行は可能です。スムーズに進めば1日で完了します。手続きの申請者は「死亡届の届出人」が理想ですが、故人様の家族であれば問題なく再発行が可能だと思います。市町村によって手続き・流れが異なりますので、詳細は窓口へお問い合わせください。
お問い合わせ
新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL. 072-234-2972