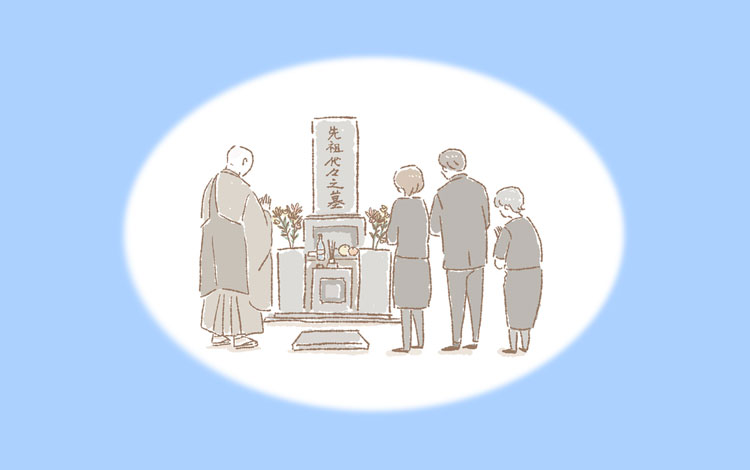先日、ある男性(Aさん)からご相談の電話がありました。
法要(一周忌法要)についてご相談なのですが、菩提寺のお坊さんから『法要を行うかは、ご家族で決めていただいて結構です』と言われたのですが、やはり法要は行うべきでしょうか?
詳しくお話を聞くと、Aさんはお父様のお葬式で喪主を務め、一周忌法要は「行わない」がAさん自身の考えのようです。ただ、おじ・おばさん(お父様の兄妹)の考えが気になるようで、とても悩んでいる感じでした。
声から想像すると40代前半くらいだと思います。たとえ喪主(遺族代表)の立場だったとしても、年齢的に目上のおじ・おばさんの考えが気になるのはとても理解できます。
ある意味「正解がない」ご相談なので、基本的な考えや他のお客様の事例などを含めてご説明しました。当社がお葬式を担当していないため、Aさんの具体的な状況が不明でしたし、地域によって風習・慣習も異なりますので、お葬式を依頼した葬儀社さんへの相談もご提案しました。
最後は声が明るくなっていただけたので、少しはお役に立てたかなと安心しました。
大前提として【法要はご家族・親族様の自由】で良いと思います。ただし、亡くなられた方、喪主、親族…それぞれの立場・考え方・状況も様々ですので、最も優先すべきは「親戚間でもめない」ことだと思います。
もしご自身がAさんと同様に、お葬式で喪主を務め、基本的に法要に関する決定権がある立場でも、目上の親戚(主におじ・おば:故人の兄弟姉妹)がいらっしゃる場合は、その方たちの意見や気持ちを尊重することも大切だと思います。
全員の意見を一致させるのは難しいですが、とにかく「もめない」ように話し合いましょう。きっと故人様もご自身の法要でもめるのは悲しむはずです。
四十九日法要・一周忌・三回忌法要まではしっかりと行う方が多いので、喪主様を中心にご家族・親族全員で話し合って決めることがおすすめです。七回忌以降は徐々に個人(各家庭)での供養へ移行していく場合が多いと思います。
法要を行うか?行わないか?はご家族様の自由ですし、法要を一切行わない方もいます
基本的に、法要はご家族・親族様の自由で良いと思いますし、誰かに強要されるものでもないはずです。
例えば、一般的な仏式のお葬式(お坊さんの読経あり)を行った方でも、法要に関しては様々です。
・四十九日法要は行うけれど、年忌法要は行わない
・四十九日法要と一周忌法要までは行う
・四十九日法要と一周忌・三周忌法要までは行う
・お葬式後の法要は一切行わない
・etc…
お葬式と同様に法要も人それぞれ価値観が異なります。どれが正解とも言えませんし、どれが間違いとも言えません。仮に同じ人であっても、その時の状況によって変化すると思います。
喪主お一人で決断をせず、ご家族・親族の皆さんでの話し合いがとても大切です。
目上の親戚(喪主であるご自身より年配者)がいる場合は、意見を聞いてみることがおすすめです
Aさんの様に、お葬式で喪主(遺族代表)を務め、基本的に法要に関してご自身に決定権がある場合でも、目上の親戚(ご自身より年配者)がいらっしゃる場合は一度意見を聞いてみることがおすすめです。
年配者には信仰心が厚い方も多いため「法要はきちんと行わないとダメ!」と言われるかもしれませんが、言い換えると「きちんと供養してあげたい」という故人様への優しい気持ちの表れだと思いますので、ゆっくりと話し合いましょう。
もし、故人の遺志で「法要は行わない」と既に決定している場合でも、しっかりと事情を説明することが大切です。ご親戚を無視したり、事後報告は避けることがおすすめです。
菩提寺(お付き合いのある寺院)がある場合
菩提寺(ぼだいじ:お付き合いのある寺院、お家の墓がある寺院)がある場合は、菩提寺に法要の相談をされるのもおすすめです。
※注:お坊さんも仕事(ビジネス)ですので、「法要を行うべきか?」と相談すると「行うべき」と言われる可能性は高いですが、何か迷われている場合は一度相談してみてはいかがでしょうか。
Aさんの様に、菩提寺のお坊さんが「法要はご家族の自由」と言ってくれるのは、とても親切なお坊さんだと思います。
お坊さんによっては、お葬式(収骨)が終わった後すぐに「49日法要は○月◯日でいかがですか?一周忌は○月中旬くらいの予定で、また後日連絡をします」と少し強引な感じで決定している場面も時々見かけます。
もちろん「お坊さんが法要を行う前提」だったとしても、「ご家族が行わないと決めた」のであればお断りして良いと思いますが、菩提寺との今後のお付き合いも考慮してご判断ください。
お葬式の時に葬儀社から「お坊さん(僧侶)を紹介してもらった」場合
お葬式の時に葬儀社の「お坊さん(僧侶)紹介」をご利用された方もいらっしゃると思います。
当社でも同様のサービスをご用意していますし、「法要を行いたいので、また同じお坊さん(寺院)を紹介してください」と利用者様から再度ご依頼もあります。
法要で再度「お坊さん(僧侶)紹介」をご希望の場合は、お葬式を依頼した葬儀社さんにご相談ください。
当社の場合、御布施(お坊さんへの御礼)の金額は「3~5万円」です。
例えば、法要場所がご自宅で「読経のみ」でしたら3万円で良いと思います。追加でお墓へ移動して「納骨式(遺骨をお墓に納める)」も行う場合は5万円など、内容にもよりますので一度ご相談ください。
法要当日、大雨が降っている・とても暑い日などの場合に「お気持ち」として少しプラス(数千円ほど)するとお坊さんも嬉しいと思います。
【参考】お葬式後の最初の法要は四十九日法要、その後は年忌法要(一周忌、三回忌、七回忌…)へ続きます
お葬式後の最初の法要は一般的に「四十九日法要」です。本来は死亡日(命日)から数えて49日目に行う方法ですが、「49日目【前】の土日祝日」に行うことが一般的です。実際には35~40日目前後に行う方が多いと思います。
その後は「年忌法要(ねんきほうよう)」が続きます。年忌法要は「該当する年の命日まで」に行います。命日を過ぎてはいけないとされています。
年忌法要は仏教で大切とされている数字「三と七」に関連して行われますが、どこまで年忌法要を行うかは自由です。一般的に、一周忌・三回忌法要まで行う方が多いと思います。
- 一周忌法要(お葬式の翌年)
- 三回忌法要(お葬式の2年後)
- 七回忌法要(お葬式の6年後)
- 十三回忌法要(お葬式の12年後)
一周忌法要は「お葬式を行った翌年」に行います。◯回忌法要は「お葬式を行った年から【(◯-1)年後】」に行います。
例えば、「三回忌は(3-1)=2年後」、「七回忌は(7-1)=6年後」です。
※一周忌と三回忌は、お葬式の翌年と2年後なので、2年続けて法要を行います。
年忌法要の最後は「三十三回忌(または五十回忌)」と言われますが、三十三回忌まで行う方は非常に少ないと思います。
私たちがお客様から聞く限りでは「三回忌までご遺族が集まって行う。それ以降は各家庭で自由に供養する」、そんな方が多いと感じます。
まとめ
基本的に法要を行うか?行わないか?は、ご家族・親族様の自由だと思います。決定する際の中心的な立場(まとめ役)になるのは「お葬式で喪主(遺族代表)を務めた人」です。具体的には「故人の配偶者または長男」が多いです。
もし喪主がご家族・親族様の中で「最年配」であれば全員の意見がまとまりやすいかもしれません。でも、まだ年齢が若い場合は「親戚の年配者(おじ・おば等)の意見も伺う」こともおすすめです。くれぐれも無視や事後報告は避けましょう。
お一人おひとりの立場や考え方も異なりますので、法要に関して絶対的な正解はありません。最も大切なのは「親戚間でもめない」ことだと思います。
法要を行う・行わないにかかわらず、故人を想う気持ちを尊重し合って、ご家族・親族が仲良く過ごしていくことが故人にとって一番嬉しいことかもしれません。
法要を行わない(行わなくなった)としても、各自でお墓参りに行く、毎日写真に手を合わせる、お花を供える、故人を思い浮かべる…それだけで十分供養になっていると思います。