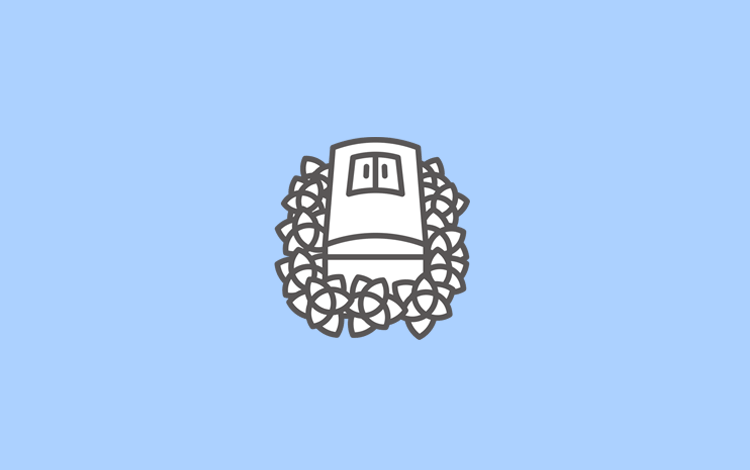甥や姪が、独身のおじ・おばさんのお葬式で喪主になる(お葬式を行う)ことは時々あります。
具体例として、本来であれば自分の父(おじの兄)が喪主になるべきだけど、父が入院中なので自分(甥)が喪主になる場合です。本来、喪主になるべき人の代理です。
そして、上記とは状況が異なるご相談として
独身(または離婚をして子がいない)のおじ・おばがいて、お葬式を行う人が親族内で自分(甥・姪)しかいない。そんな場合、甥・姪が「独身のおじ・おばさん」のお葬式を行う【義務】はあるんですか?
※おじ・おばの兄弟姉妹はすでに亡くなっている。
先に結論をお伝えすると、故人と同居していない親族には、ご遺体の引取りや火葬・埋葬(遺骨の供養)をする義務はない」と考えられます。親族には甥・姪も含まれますので、同居していなければ「義務はない」ことになります。
実際、故人の兄弟姉妹であっても「迷惑をかけられた」等の理由で拒否をする方もいますし、親族間での関係性や事情は様々です。
今回は、お葬式の義務について法律も含めて少しお話したいと思います。
おじ・おばを漢字で書くと
・伯父・伯母 ⇒ 父母の兄・姉
・叔父・叔母 ⇒ 父母の弟・妹
と違いがありますので、このページでは「おじ・おば」で統一しています。
甥や姪が独身のおじ・おばさんの「お葬式や遺体引取り」をする義務はある?
ご家族・親族の構成によっては、突然、病院や役所、警察からおじ・おばさんの死亡連絡やご遺体の引取り連絡が、甥・姪に入る可能性もあります。
- おじ・おばさんが独身
- 結婚はしたけれど配偶者に先立たれ、子もいない
- 離婚をして子がいない
- おじ・おばさんの兄弟姉妹がいない(既に死亡)
などの場合は、残った親族(甥・姪)へ連絡がいく可能性が高いです。これは法律で決まったルールではなく「とにかく連絡が取れる親族へ」という流れです。
そして、冒頭でお伝えしましたが、
【故人と同居していない親族には、ご遺体の引取りや火葬・埋葬(遺骨の供養)をする義務はない】と考えられます。
親族には甥・姪も含まれますので、同居していなければ「義務はない」ことになります。
その理由に関連する、お葬式と遺体引取りの義務について簡単にご説明します。
お葬式(宗教儀式)を行う義務は誰にもありません
まず最初に、「お葬式は誰が行うべき」と定められた法律はありません。
お葬式(宗教儀式)を行うことは誰の義務でもありません。お葬式は昔から故人の家族・親族が行うが「慣習」であって、法律で定められた義務はありません。結婚式を行う義務がないのと同じです。
「友人がお葬式を行えますか?」と時々ご質問を受けますが、問題は「死亡届の届出人」です。
死亡届の届出人は基本的に「親族」です。単なる友人の立場では届出人にはなれません。
死亡届を提出できないと火葬許可証が発行されません。つまり、お葬式・火葬ができません。また、友達では故人の財産から葬儀費用を支払うこともできません。
誰にもお葬式をする義務はありませんが、死後の事務手続きができる人は限られています。一般的には、故人の遺産相続も関わりますので「ご家族・親族が死亡届の提出やお葬式を行うのが普通」というのが当然ということですね。
ご遺体の引取りは「同居の親族」に義務があり、「同居していない親族」には義務はありません
次に、ご遺体の引取りについて。
お葬式と同様に「ご遺体の引取り」を明記した法律は見当たりません。ただし、関連する法律が2つあります。
- 墓地、埋葬等に関する法律
- 戸籍法
1.「墓地、埋葬等に関する法律」
「死体の埋葬または火葬を行う者がいない時、判明しない時は死亡地の市町村長(大都市は区長)が行わなければならない」
ここには「家族・親族の義務」については明記されていません。あくまで【埋葬や火葬は故人の家族・親族が行う】が前提だと思います。
では、「誰にも遺体の引取り義務が無い?」となりますが、もう1つの法律(戸籍法)が関係します。「死亡届の提出義務」に関する法律ですが、実際は死亡届の提出だけを済ませて、ご遺体を引取らない事は不可能です。
2.戸籍法(86条・87条)
- 86条【死亡届の提出期限・添付書類】
死亡届は届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければならない。死亡届には死亡診断書(又は死体検案書)を添付しなければならない。 - 87条【死亡届の届出義務者】
次の者は、その順序に従って「死亡届」を提出しなければならない。- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
上記以外には、同居していない親族も提出することができる。
※全体的に分かりやすい言葉に少し変換しています。
死亡届の提出に必要な死亡診断書は、ご遺体の引取りと同時に病院から受け取ります。そして、ご遺体を引取った以上は最低限火葬が必要です。
つまり、「ご遺体の引取り+死亡診断書の受取 ⇒ 死亡届の提出 ⇒ 火葬・埋葬」までを含めて義務になると考えられます。
まとめると、故人と「同居していた親族」には以下の義務があることになります。ポイントは「故人と同居しているか?していないか?」です。つまり、故人と同居していない親族、甥・姪には義務はありません。
- ご遺体の引取り
- 死亡届の提出
- お葬式を行わないとしても火葬・埋葬(遺骨の供養)
「故人と同居していない親族」の中には、実際に「引取り拒否」をする方もいます
ご説明したように、「故人と同居していない親族」にはお葬式や遺体の引取り義務はないと考えられます。
実際、故人の兄弟姉妹であっても「生前に散々迷惑をかけられたから、これ以上関わりたくない!」とご遺体の引取りを拒否される方もいらっしゃいます。
「他の親戚が拒否をしたので、甥の私へ警察から連絡が来ました」、「ご遺体の引取りをお願いします」と警察官が自宅まで来る場合もあります。
故人の私生活が不明だった場合の遺産相続は慎重に考えましょう
ご遺体引取り時点で、故人の遺産を把握することは難しいです。仮に、故人の金融口座に残高があっても、隠れた借金があればトータルでマイナスの可能性もありますし、不用意に遺産に手をつけると相続放棄もできなくなります。
故人の私生活が不明だった場合の遺産相続は慎重に考える必要があります。まずは、相続の専門家(弁護士・司法書士など)へのご相談がおすすめです。
【実話】本家の跡継ぎAさん(甥)が喪主?
Aさんの父は本家の長男で既に死亡していました。そして、分家で独身のおじ(父の弟)が死亡した時、おば(父の妹)2人から「本家の長男の子だから、あなたが葬儀をやるべき」と強く迫られたそうです。
Aさんは「父がいれば喪主を務めるだろうけど、甥の自分よりおばさんが喪主になるべきだ」と言いましたが、結局Aさんが葬儀を執り行いました。葬儀社の手配や費用面でおばさんの援助は無かったそうです。
そして、おじさんの遺産の相続人は「Aさんとおばさん2人」
葬儀費用等を差し引いて分割すれば済む話でしたが、葬儀・遺品整理などを全部押し付けられた上に、「残った財産は均等」にAさんは納得できない部分もありましたが、親族で争いたくないのでAさんは受け入れました。
未だに本家・分家の概念は残っていますが、法律で「◯◯が喪主」という決まりもありません。基本的には、故人の配偶者や長男が喪主になる場合が多いですが、喪主1人がすべてを負担する義務もありません。
喪主になるべき人が海外在住の場合もあります。家族葬が増えている現在では、ご家族・親族みんなで協力してお葬式を行うことが大切だと思います。
お葬式と遺体引取りの義務についてのまとめ
ここまでの内容をまとめると、
- お葬式(宗教儀式)を行う義務は誰にもありません
- 「同居の親族」には死亡届の提出義務がある
- 死亡届の提出する=「遺体の引取り・死亡届の提出・火葬(埋葬)」までが含まれる
- 同居していない親族には、上記の義務はない
つまり、故人と同居していた親族には「最低限の弔いの義務がある」という事になります。反対に、同居していない親族には、それらの義務はありません。
冒頭の質問に戻ると、【独身のおじ・おばさんと同居していない甥や姪には、おじ・おばさんのお葬式や遺体引取りの義務は法律上ない】という事になります。
良い悪いは別として、世の中は慣習や一般常識でうまく回っている部分もあると思います。法律に明記されていない部分を補っている感じかもしれません。
お葬式で言えば、「喪主は長男!」が暗黙のルールです。きっと不平等と感じる人も多いですし、全員が納得するのは難しいです。でも、受け入れてくれる人がいるからこそ物事が前に進みます。喪主1人に押し付けず、お互いに助け合う気持ちが大切だと思います。
【参考】甥・姪がおじ・おばさんのお葬式で喪主になる場合
ここから先は、甥・姪が喪主になる場合のお葬式について簡単に説明します。基本的には通常のお葬式と特に変わりはありません。まずは、下記の3点をご用意ください。
- 死亡診断書:病院や施設で受け取ります
- 印鑑:喪主になる方(朱肉を使うもの)
- 故人様の写真:遺影写真を作成する場合
菩提寺(お付き合いのあるお寺)やお墓を確認
菩提寺やお墓の有無を確認しましょう。もし菩提寺内にお墓がある場合、納骨条件は「戒名を授かる」が基本です。そのため、菩提寺を無視すると納骨を断られる可能性もあります。
また、直葬(火葬のみ)をご希望の場合、「火葬だけなので、お坊さんは必要ない」と思われるかもしれませんが、菩提寺には連絡が必要です。
収骨をするか?しないか?
原則は「収骨あり(お骨上げをする)」ですが、「収骨なし」も可能です。収骨をしなかった遺骨は、各市町村が供養(合祀墓や提携寺院など)してくれます。ご希望の場合は「火葬日の前日まで」にスタッフにご相談ください。
【参考】おじ・おばさんの遺産を相続したくない
もしご自身が、おじ・おばさんの法定相続人に該当する場合は「遺産を相続するか?しないか?」を考えておくことも大切です。
遺産相続はプラスの遺産(預貯金・不動産など)とマイナスの遺産(借金・未払金など)の両方を相続することになります。もし、遺産(借金を含む)を相続したくない場合は「相続放棄」の手続きが必要です。
下記の様な場合は、相続放棄がおすすめです。
- 故人に借金があるかもしれない
- 面倒なトラブルに巻き込まれたくない
- 不安要素を無くしたい
甥や姪の方が、おじ・おばの「法定相続人」に該当するケース
正式には、故人の戸籍を調査する必要がありますが、下記の条件が重なった場合に、甥・姪が法定相続人に該当する可能性があります。ご不安のある方は専門家(弁護士・司法書士など)へのご相談がおすすめです。
- 故人(おじ・おば)が未婚
- 故人(おじ・おば)に子がいない
- 故人(おじ・おば)の両親や兄弟姉妹が既に死亡している
故人の遺産を相続する人には「順位」があります。上位の人がいない場合に「1⇒2⇒3⇒甥・姪」と順番に相続権が移ります。
故人(おじ・おば)に配偶者や子・孫、両親(祖父母)もいない、兄弟姉妹も既に死亡している。そんな場合に、甥や姪が相続人になります。
- ※常に相続人:故人の配偶者
- 第1位:故人の子(孫)
- 第2位:故人の両親(祖父母)
- 第3位:故人の兄弟姉妹
- 第4位:故人の甥・姪
相続放棄をする場合の期限は3か月以内
相続放棄の期限は「自身が法定相続人に該当すると知った時から3か月以内」です。
相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要です。費用はかかりますが専門家(弁護士・司法書士など)への依頼がおすすめです。ご希望の場合は専門家をご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
甥や姪がおじ・おばさんのお葬式を行うと言っても、立場・状況は様々です。
本来は他の親族が喪主になるべきだけど、ご高齢や病気のために甥・姪が代理で行う場合もありますし、故人の親族が甥・姪しかいない場合もあります。ほとんど会ったことがないおじ・おばさんのお葬式を手配する方もいます。
甥・姪が喪主になったとしても、通常のお葬式と特に変わりません。お葬式後の遺産相続や遺品整理などもサポートいたします。何かお葬式に関してご不安をお持ちの方は、まずは一度ご相談ください。
【補足】法律上の家族・親族の「助け合い」について
家族や親族間の「助け合い」に関する法律はいくつかあります。
- 民法 730条(親族間の扶け合い)
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 - 民法 752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 - 民法 877条(扶養義務者)
第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 - 民法 877条(扶養義務者)
第2項 家庭裁判所は特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間(※)においても扶養の義務を負わせることができる。
※「おじおば、甥姪、その各配偶者など」
- 扶助:力添えをして助けること。
- 扶養:自力で生活できない者の面倒をみ、養うこと。
簡単に言えば「家族や親族はお互いに助け合いましょう」ということですね。「助け合い」の内容は少し曖昧ですが、「葬儀」も助け合いの1つだと思います。でも、円満な家庭・親族関係ばかりではありませんし、ご遺体の引き取りを拒否をした(したい)方の理由を聞くと理解できる部分もあります。
法律は人の感情や事情を考慮してくれないので、お葬式やご遺体引き取りを強制するのは難しいと思います。故人の家族・親族が最期を見送ることは世間一般的には当然のように思われていますが、それをしてもらえる事自体とても幸せなことかもしれませんね。
お問い合わせ
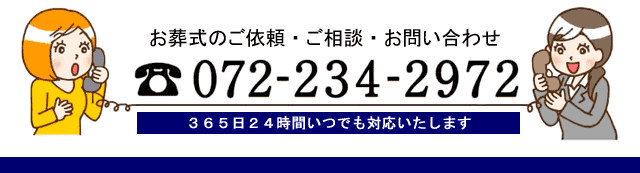
新家葬祭
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL: 072-234-2972 【24時間365日受付】