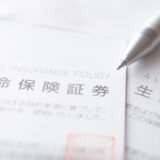「私が死んだら、◯◯をあげるね」という会話は、冗談を含めて時々聞きます。でも、もし真面目に「口約束」をした場合、有効になると思いますか?
例えば、姉A・妹Bさんがいました。姉Aは趣味で野菜を育てていた「畑(土地)」を所有していました。姉Aが「私が亡くなったら、Bに土地をあげるね」と言い残し亡くなりました。この場合、妹Bは姉Aの言葉を「遺言」として、土地がもらえるのでしょうか?
まず、弁護士・司法書士さんに聞いてみたところ、単なる「口約束」では遺言に当たらず、法的効力は無いようです。遺言や契約は「書面」で残すことが原則だからです。でも、口約束が全く無意味とも言い切れません。もし相続人全員が納得すれば、口約束通りに相続を進めることも可能です。
やり取りの証拠(契約書)があることが一番だと思いますが、実際の相続では「あなたが介護してくれたから助かった」など相続人(ご家族・親族)同士での思いやりもとても大切だと思います。
贈与者(財産をあげる人)の死亡で発生する「贈与」は2種類
贈与者(財産をあげる人)の死亡を原因として効力が発生する贈与には、【遺贈】と【死因贈与】の2種類があります。
両方とも、特定の人に財産を与えることが可能です。大きな違いは「受贈者(財産をもらう人)の合意があるか?ないか?」です。
- 遺贈(遺言書)
受贈者(財産をもらう人)の合意なし。 - 死因贈与(私が死んだらあげる)
受贈者(財産をもらう人)の合意あり。
1.遺贈(遺言書)
【遺贈】は、一般的に知られている「遺言書を作成して、特定の人に財産をあげる」ことです。法的にも有効です。贈与者(財産をあげる人)の単独行為(一方的な意思表示)で可能です。
2.死因贈与(私が死んだらあげる)
今回のケースである【死因贈与】は、贈与者(財産をあげる人)が「私が亡くなったらあげるね」と贈与の意思を示して、受贈者(財産をもらう人)が「いいよ!」と双方が合意すれば、基本的に契約が成立します。
ただ、姉Aが真面目に「(妹Bに)畑をあげる」言ったとしても、遺言(法的効力あり)には当たりません。遺言は「書面で残す」が原則だからです。
この場合、妹Bが「姉Aが私に土地をあげる」って言ってたと主張しただけでは、死因贈与は認められにくく、認められるには2つの条件が必要です。
1.「死因贈与契約書」
贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)との間で契約書を作成し、お互いの署名捺印があれば有効な証拠と考えられます。
また、姉Aと妹Bのやり取りを「実際に見聞きした証人」がいれば、証拠として役に立つ可能性もあります。
2.「相続人全員の承諾」
相続人が複数(妹B以外にも)いた場合、相続人全員が納得をすれば死因贈与契約の内容通りに相続が可能です。
ただし、死因贈与契約の内容について意見が分かれる可能性もあり、誰か1人でも反対者がいれば成立させることが難しくなります。
基本的に「死んだらあげる(死因贈与契約)」は「撤回」も可能です
遺言書が自由に何度も書き直しができるように、死因贈与契約でも贈与側(財産をあげる人)は、基本的にいつでも撤回できるとされています。
ただし、遺言書とは異なり死因贈与契約は「双方の合意」で成立しているので、きちん相手側に撤回の意思を伝えなければ後々トラブルになるケースもありますので注意が必要です。
撤回できない「負担付き死因贈与契約」
死因贈与でも撤回が認められないケースもあります。それが「負担付き死因贈与」です。「介護してくれたら、財産をあげる」など、受贈者(財産をもらう人)に一定の条件(義務)を負担させる契約です。
実際に、受贈者(財産をもらう人)が条件を実行していた場合は、特別な理由がない限り撤回が認められない可能性もあります。
例えば、介護が必要な父Cが長男Dに
「同居して介護してくれたら、自宅をあげるよ」と言って、長男Dが「分かった。それなら介護するよ」と負担付き死因贈与契約を結んだとします。
しかし、長年介護を続けたにも関わらず、親子喧嘩を理由に父Cが「死因贈与は破棄する!お前には自宅をわたさない!」と契約破棄が認められるのであれば、約束どおり介護をした長男Dがかわいそうです。
そのため、特別な理由がない限りは、受贈者の権利保全のため自由に破棄できないとされています。
遺贈(遺言書)と死因贈与は、どちらが優先される?
仮に、「遺贈(遺言書)」と「死因贈与の契約書」がどちらも見つかった場合、最新の日付の方(最後に作成された方)が優先されます。
遺言書には日付記載が必須ですので作成日が明確です。しかし、死因贈与契約書は日付記載が必須ではないため、日付がない可能性もあります。この場合は、遺言書が優先されます。
遺贈(遺言書)や死因贈与をお考えの方は専門家に相談しましょう
何か事情や理由があって、ご自身の財産を「特定の人」へ残したい場合は、相続の専門家(弁護士・司法書士など)へのご相談がおすすめです。公証役場へのご相談も良いかも知れません。
どのような方法・選択肢があって、何が最適なのか?費用はどのくらい必要なのか?まずは専門家に相談してからゆっくりとお考え下さい。
お問い合わせ
新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL: 072-234-2972 【24時間365日受付】