追記裁判所HP・司法統計年報によれば、
- 2019年(令和元年)相続放棄件数は約22万5千件
- 2020年(令和2年)相続放棄件数は約23万5千件
少しずつですが年々増加傾向です。
「相続放棄」が世間に浸透してきているのでしょうか?今度、弁護士や司法書士の方とお会いした際に、増加理由があるのか質問してみたいと思います。
また、相続放棄とは少し異なる話ですが、2024年から「相続登記」が義務化になります。故人の財産に不動産が含まれる場合、名義変更が必要になります。ただし、不要な土地に対しては所有権放棄を認める制度も創設されるようです。
故人の遺産を受け継がない「相続放棄」が増えています。裁判所HP・司法統計年報によると
- 平成20年(2008):約14万件
- 平成30年(2018):約21万件
10年間で約1.5倍です。
相続はプラス財産だけではなく、マイナス財産(借金など)も受け継ぎます。
被相続人(故人)が【それなりの預貯金と立地の良い不動産】を残した場合は、メリットがあると思います。
反対に【少額の預貯金と立地の悪い不動産】を相続すると、不動産が売却できずに管理費や税金の負担で赤字になる可能性もあります。
そのため、デメリットが大きい場合は「相続放棄」をして面倒な義務から解放されたい気持ちはわかります。ただし、「相続放棄 ⇒ 後は一切関係ない」では済まされない場合もあります。
【管理責任】
例えば、被相続人(故人)が不動産を所有していた場合、相続放棄をしても「その不動産の管理責任(管理義務)」は残ります。新たな相続人(管理人)が見つかるまでは、管理する義務があるということです。管理を怠ると損害賠償請求を負う可能性もあると考えられます。
相続放棄や管理責任の詳細は非常に複雑な内容になるので、このページでは概要をシンプルな説明にしたいと思います。
もし、相続放棄でお悩みの場合は、できるだけ早く弁護士や司法書士へのご相談がおすすめです。
相続放棄の基礎知識など
司法統計や人口動態統計データから単純計算をすると、
2008年の死者数:114万2千人、相続放棄:約14万5千件⇒約12.7%
- 1,000人あたり:127件
- 100人あたり:12.7件
2018年の死者数:136万2千人、相続放棄数:21万件⇒約15.4%
- 1,000人あたり:154件
- 100人あたり:15.4件
単純計算ですが想像より多いですね。実際には、都道府県(市町村)でバラつきがあると思います。大阪府内の市町村別データは見つけることができませんでした。
相続放棄は被相続人の死亡を知ってから3か月以内
遺言書がない場合、法定相続人(民法で定められた相続人)が財産を相続します。多くの場合、法定相続人は「故人の配偶者+子」または「子のみ」になります。
そして、相続放棄の期限は自分が相続人と知ってから「3か月以内」です。一般的には、自分の両親(父または母)が死亡した日から3か月以内とお考え下さい。
相続放棄は、ご家族・親族全体で考える必要があります
相続放棄をすると相続権が【第1⇒ 第2⇒ 第3】と順番に移ります。第1位:子が放棄すると、第2位:両親へ移ります。
つまり、ご自身が相続放棄をすることで、他の親族へ相続権が移る場合があります。そのため、相続放棄はご家族・親族を含めて全体で検討する必要があります。
逆に、ご親戚が相続放棄をしたことで、相続権がご自身に回ってくる場合もあります。自分が相続人になると想像もしていないケースです。その場合、相続放棄の期限は「自分が相続人に該当すると知った時点」から3か月以内です。
相続放棄の申請は1度だけ
申請は1度のみで、書類ミスだけでも再申請はできません。また、正式に受理されると撤回ができません。
3か月以内に財産を把握し、相続人を確定して相続するか?しないか?を決定する必要があります。期限が短く、ミスができませんので、専門家への依頼がおすすめです。
▼▼補足情報
すべての相続人が相続放棄をしたことで、相続人が不存在(誰もいない状態)になった場合、相続財産は法人化(⇒相続財産法人)され、相続財産管理人が管理・清算をします(民法第951条、第952条)。そして、最終的に残った財産は国庫に引き継がれます(国庫帰属)。
難しい言葉が並んでいますが、被相続人(故人)の財産に対して「誰も何もしない状態」は国も困ります。
そのため、本来の相続人である家族・親族に代わって、相続財産管理人に選ばれた人が被相続人の財産の清算手続きをしてくれるということです。
相続財産管理人は、家庭裁判所が選任します(弁護士さんが選任されることが多いようです)。選任には、家庭裁判所へ相続財産管理人選任審判の申立てが必要です。申立てができる人は「利害関係人」と「検察官」です。
利害関係者とは、「被相続人の債権者、特定遺贈の受遺者、特別縁故者、被相続人と財産を共有している人、相続放棄した元相続人や元包括受遺者など」です。
また難しい言葉が並びますが、例えば被相続人の財産は遺言書が無ければ法定相続人が相続します。仮に法定相続人全員が相続放棄をしたとしても、お金を貸していた人(債権者)へ自動的に財産から返金される制度はありません。債権者がお金を取り戻したい場合は相続財産管理人の選任申立てが必要です。
通常、相続放棄をした人が申立てをする必要はありませんが、不動産や自動車など管理が必要な財産については相続財産管理人が必要な場合もあります。
関連する法律
- 民法第940条
- 民法第918条
- 民法第27条
- 家事事件手続法201条
相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てする際の基本的な費用として、以下の3つが必要です。
- 収入印紙800円
- 切手代(裁判所からの連絡用。裁判所によって異なりますが1000円前後のことが多いようです。)
- 官報公告料3775円
また、上記費用とは別に、選任請求をした人が「予納金」というお金を裁判所に納める必要がある場合があります。
相続財産管理人の報酬は基本的に相続財産の中から支払われますが、相続財産の価額が少ない場合、家庭裁判所は申立人に予納金の納付を命じ、相続財産管理人の経費や報酬は予納金から支払われます。
予納金の金額は、管理の手間や事案の難易度に応じて「数十万円~100万円程度の範囲」で家庭裁判所が決定します。
相続財産管理人の業務が終了した時点で、遺産から十分に報酬の支払いが出来る場合には予納金は返ってきますが、足りない場合は予納金から支払われるので返ってきません。
相続放棄をしても「管理責任(管理義務)」は残ります
問題はこの部分です。
原則として、相続放棄をすれば、相続人はすべての権利や義務を受け継ぎません。しかし、「相続放棄 ⇒ 後は一切何も関係ない」では済まない場合もあります。
民法第940条には、下記の様に書かれています
相続放棄をした者は、その相続放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
法第940条
これは、売却が難しい山林や空き家など、価値がない不動産の管理を免れたい理由で相続放棄した場合でも、新たな相続人(管理者する人)が見つかるまでは、きちんと管理する「義務」があるということです。
不注意で財産を毀損した場合、債権者などから損害賠償請求を受けるかもしれませんし、管理不行き届きで周辺住民に損害を与えたりすると、同じように損害賠償請求を受ける可能性もあります。
いわゆる、「負動産」が財産に含まれる場合、相続人は困ります。自分が住む予定がない。売るに売れない。借り手も見つからない。更地にしても有効な利用方法がない。相続すると固定資産税が掛かる。そういった不動産は相続したくないのは誰もが同じだと思います。
責任の所在は曖昧になりがちなようです
本来、相続放棄した人でも新たな相続人に引き渡すまでは、空き家などの不動産を管理する義務があるとされていますが、実際には責任の所在は曖昧のようです。民法940条をご存知でない専門家もいると聞いたことがあります。
現状、不動産の名義人(所有者)が死亡した場合、相続登記(不動産の名義変更)は義務ではないため放置している方も多いです。
追記
2024年から「相続登記」が義務化になります。
昔は長男が家督を継ぐことが一般的でしたので、長男家族がそのお家に住み、固定資産税を支払っていました。でも、時代が変わり、きちんと名義変更をしようとしたら、相続人が数十人に膨らんでいる事は少なくありません。
街中の「空き家」問題
最近増えている街中の空き家も、相続人が不明、相続人が多数で同意が得られないため放置されているケースが多いようです。名義変更を義務化していなかったために、今になって国も困っている感じだと思います。
人口減少で過疎化が進んだ土地は価値が下がります。そうなれば、さらに相続放棄も増えるとの指摘もあります。人口減少と関連して、年金やお墓の承継者などの問題が取り上げられますが、相続もかなり深刻化してきそうですね。
負担になるだけの財産は、誰でも困ります
将来、相続登記を義務化にしたり、相続放棄をしやすいように国も法改正に向けて進んでいるようですが、いろいろと難しそうですね。
相続放棄を希望する人は「すべての権利を放棄するから、家族や遠い親戚の面倒な財産や管理から解放されたい」という人が多いです。
時には、ほとんど面識のない親戚の相続権が自分に来ることもあります。「誰が相続人になるか?」は、死亡した順番でも変わります。現状の家族・親族構成だけで決定するものではありません。
突然、自分が想像もしていない人の相続人になり、その財産に「負動産」が含まれていたら、相続したくない気持ちは十分理解できます。
- 相続放棄をしても管理責任がある
- 相続をしても、売却できないと固定資産税がかかる
- 更地にするにも解体費用がかかる
負担になるだけの財産を無理に押し付けられても、誰でも困ってしまいます。
市町村も困っていると思います
一方で、長年放置されたボロボロの家屋が街中に増えると安全性にも問題ありますし、地域住民はもちろん、市町村も困ります。かと言って、税金ですべて綺麗にはできませんし、所有者を無視することもできません。
非常に解決が困難な問題だと思いますが、税金を無駄な建物や事業に使用するくらいなら、この問題解決に使っても良いと思います。そして、相続人の負担軽減を最優先に対策を考えて欲しいですね。
法的な権利・義務のお悩みは、法律の専門家へ相談しましょう
もし、私自身が相続問題に直面した場合は、すぐに弁護士・司法書士などの専門家に相談をします。相続放棄の期限が3か月以内と短い理由も1つですが、相続問題は時間をあまり空けない方がおすすめです。
法的な権利・義務に関するお悩みは、やっぱり法律の専門家への相談が最善の方法だと思います。
お問い合わせ
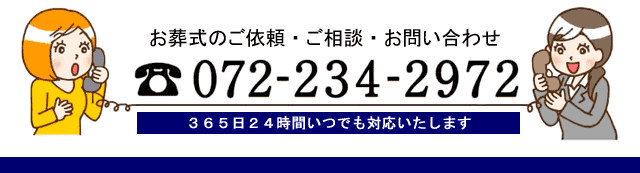
新家葬祭
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL: 072-234-2972 【24時間365日受付】


